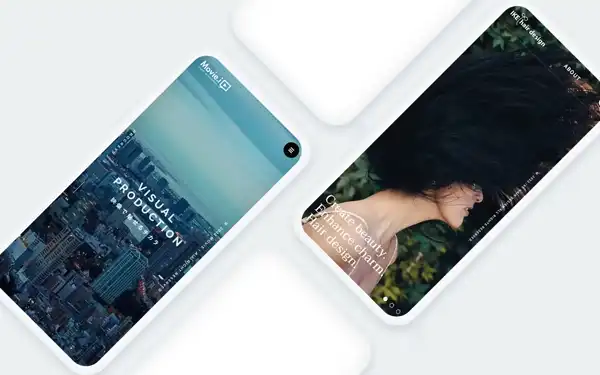ゆく年くる年、午年なので、馬の話をする

このタイミングでブログを書くことにした。
理由については、まあ各々察してほしい。
正月明けというのは、だいたいそういう時期だ。
というわけで、今日の話題は表題の通り「午年」の話である。
前提
まず前提として、一つだけ置いておく。
我々が「去年」「今年」「来年」と呼んでいる区切りは、厳密に言えば虚像だ。
時間は常に現在として流れており、過去に触れることはできず、未来は予測でしかない。
年を区切るという行為そのものが、人間にとって都合のいい慣習にすぎない。
この話を突き詰めると、人間の弱さだの認識の限界だの、だいぶ面倒な方向に進んでしまう。
なので今回は、その辺りの話は一切しないことにする。
同じ理由で、十二支がなぜ存在するのか、という話も深入りしない。
多くの人にとっては、知らないままのほうが幸せな類の話でもあるからだ。
ここでは、あくまで歴史的な文脈だけを軽くなぞる。
十二支とは何か。
Wikipedia的にまとめると、だいたい次のような概念になる。
十二支は中国発祥の体系で、東アジアに広く広まった。
十干を「天干」と呼ぶのに対し、十二支は「地支(ちし)」とも呼ばれる。
起源は紀元前16世紀ごろの殷の時代まで遡り、当初は日付の呼び名として使われていた。
戦国時代には、年・月・時刻・方位を表す記号としても用いられるようになる。
そして秦の時代までに、現在よく知られている「動物との対応関係」が付け加えられた。
https://ja.wikipedia.org/wiki/
ここで重要なのは、
十二支そのものは非常に古い概念だが、
それに付随する占いや意味づけの多くは、かなり後世の“後付け”だという点である。
つまり、現代における十二支のイメージは、
学問的必然というより、文化的に醸成された解釈の集合体だと言っていい。
では、午年とは何なのか?
ここでいきなり運勢の話をするつもりはない。
まず考えたいのは、「午」、つまり馬という生き物を、我々がどのような存在として捉えてきたか、という点だ。
馬の特徴を雑に挙げると、こんな感じになる。
- ・目は頭の側面についている
- ・鼻先が前に突き出している
- ・長距離を走れる
- ・蹄がある
- ・尾とたてがみがある
- ・毛色は茶色、白、黒など
- ・かつては移動手段として使われていた
こうした特徴を持つ存在を、我々は「馬」と呼んでいる。
ではなぜ、この生き物が十二支の一つとして選ばれたのか。
それは単に、人間と長く共に生きてきたから、という理由だけではない。
馬は役割としても、象徴としても、非常にわかりやすく“モデル化”しやすい生き物だった。
午年という概念の背後には、その象徴性が静かに横たわっている。
なぜ、人は馬を象徴にしたのか?
馬というのは、肉食動物とは異なり、牙を持たず、獰猛さもない。
同じ草食動物で言えば、鹿ほど臆病でもないし、象ほど圧倒的でもない、ちょうど良い中途半端さなのである。
そして、手なづけることで人間の思惑通りに行動してくれるし、現代でも乗馬や競馬といった娯楽の中核を担う存在でもある。
人間にとっては、速さ・力・持続・感情が、ちょうど会話できる範囲にあったのだろう。
馬は「支配できた動物」ではなく、「意思を持ったまま協力できた動物」だった。
完全な道具じゃないし、かといって神格化するほど遠くもない。
人は「馬」を象徴化したが、同時に「馬に何かを足した存在」も量産した。
例えば、ユニコーンやペガサスなどがそれにあたる。
角を一本足した => ユニコーン
翼を生やした => ペガサス
つまり、過度に神格化することは出来ないが、ちょっと神に近づける余地があるという文脈もまた人間は想起している。
一方で、なぜ「普通の馬」が消えなかったのか?
ユニコーンもペガサスも、象徴にはなったけど、生活の象徴にはならなかった。
触れない、乗れない、一緒に汗をかかない、神話には住めるけど、人間の隣には立つことは出来ないのだから関係性として弱い。
つまりは、角が一本生えた瞬間、馬は神話に引っ越した。
翼が生えた瞬間、馬は空へ逃げた。
でも、何も生えなかった馬だけが、人の横に残った。
そういった文脈もあり、現実に触れられる存在が象徴化したのかもしれない。
なぜ、シマウマではダメだったのか?

さて、先に述べた馬の普遍において、毛の色について「縞々」を除いたことにお気づきだろうか。
我々は馬とシマウマを明確に区別している。
シマウマは家畜化できず、気性が荒いし。
群れの論理が人と噛み合わない。
何より、人の隣に立たない。
馬とシマウマは人間との関係性が乖離している。
例えば、ナショナルジオグラフィックなど野生動物の捕食シーンが撮影される場合、肉食動物に狙われるのは大抵シマウマのようなものになる。
シマウマが捕食されるシーンは人間にとって関係性が薄く耐えられるが、馬が捕食されるのは耐えられない。
馬は、人を仲間でも捕食者でもなく、「一緒に動く存在」として認識した。
だから人は馬に名前をつけ、感情を読み取り、象徴にまで昇華した。
一方でシマウマにはそれが希薄であると言える。
まとめ
こうして振り返ってみると、午年や十二支というものは、誰かが「信じろ」と言ったから信じられているわけではないように思える。
それが正しいのか、意味があるのか、そもそも信じているのかどうかすら、多くの人は深く考えたことがないだろう。
ただ、気づいたときにはそこにあって、暦に載り、会話に混ざり、「今年は午年だね」と、何の違和感もなく口にできる。
それはもはや、誰の判断なのか分からないくらい自然に、環境として置かれているものなのだと思う。
馬が象徴になり、ユニコーンやペガサスが神話へと去り、それでも何も生えなかった馬だけが人の横に残ったように、十二支もまた、強く主張することなく、生活の中に溶け込むかたちで残り続けてきた。
午年だからといって、無理に走る必要はないし、何かを信じ直す必要もない。
ただ、前を向いて、自分の歩幅で進めばいい。それくらいの距離感で付き合えるものこそが、長く残るのかもしれない。